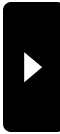2013年10月24日
こんな人ほどお金の勉強が必要~ もう一つ学ぶべき事は、生きていく上で大事な・・・
【人の心に灯をともす】より・・・
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
世の中には、「いい人」と呼ばれる人がいます。
やさしくて、どんな人にも親切で、困った人を見ると放っておけない人。
愛のある、すばらしい人です。
ところが、こういう人たちが、すべて成功しているかというと、残念なことに違うのです。
これには、神さまからのメッセージがあります。
それは、「いい人の部分は大事にしながら、
さらに学ばなければいけないことがあるよ」ということです。
では、さらに学ばなければいけないことは何でしょうか?
それは二つあります。
ひとつは「お金のこと(経済)」です。
いい人なのに、お金が入ってこない…というのは、
あなたが「よかれと思ってやっている何かが、まちがっている」ということです。
あと、ひとつ、学ぶべきことは「人間関係」です。
「いい人」は、やさしいので、すべての人にやさしくすることがいいことだと思っています。
でも、そうではないのです。
あなたのエネルギーを奪っていくような人や、
あなたをなめてかかるような人にまで、やさしくしてはいけません。
自分が嫌われないように、「ビクビクした波動」を出すこともありません。
あなたと波長の合う人とだけ、楽しくやっていけばいいのです。
実は、「いい人」こそ、成功して豊かにならなければいけないと私は思っています。
なぜなら、「いい人」のところにお金が集まれば、「いいこと」にお金を使うからです。
「ろくでもない人」のところにお金が集まれば、「ろくでもないこと」にお金を使うでしょう。
また、お金がなければ、愛する人が困ったときに、助けてあげることができません。
「お金(経済)に強くなる」ために、最初にしなければいけないことは何でしょうか?
それは、“赤字”を出さないことです。
いままで貯金をしたことがない人は、いままでより少ない金額でやりくりする工夫をして、
月に1万でも、2万でも、貯めていく。
それができれば合格です。
それだけを心がけていればいいのです。
この「マイナスをつくらないこと」は、商売や仕事をやるうえでも、もっとも大切なことです。
商売や仕事で使うお金のことを「出金」といいます。
この「出金」を、最初から、できるかぎり減らすことです。
「儲け」を出す前に、商売道具にお金をかけてしまうことは、一番やってはいけないことですからね。
『人とお金』サンマーク出版
今年10月、伊勢神宮では20年に1度の御遷宮が行なわれた。
約1300年にわたって営々と続けられている行事で、今年は62回目の式年遷宮となる。
東の御敷地から、西の御敷地に遷(うつ)られたが、
それを米座(こめくら)から、金座(かねくら)に御遷りになった、という言い伝えがあるそうだ。
米座の時代は、平和で心豊かな「精神の時代」で、金座の時代は、動乱と激動の「経済の時代」。
いよいよ、これからの時代は、精神だけでなく、
誰もが経済やお金を学ばなければならない時代に入ったようだ。
「入るを量(はか)りて出ずるを為す」という言葉がある。
収入がどれくらいあるかを計算し、それに釣り合った出費をすることを言う。
「お金の基本は、まず赤字を出さないこと」

【お金】
いい人であればあるほど、お金の勉強は必要だ。
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
世の中には、「いい人」と呼ばれる人がいます。
やさしくて、どんな人にも親切で、困った人を見ると放っておけない人。
愛のある、すばらしい人です。
ところが、こういう人たちが、すべて成功しているかというと、残念なことに違うのです。
これには、神さまからのメッセージがあります。
それは、「いい人の部分は大事にしながら、
さらに学ばなければいけないことがあるよ」ということです。
では、さらに学ばなければいけないことは何でしょうか?
それは二つあります。
ひとつは「お金のこと(経済)」です。
いい人なのに、お金が入ってこない…というのは、
あなたが「よかれと思ってやっている何かが、まちがっている」ということです。
あと、ひとつ、学ぶべきことは「人間関係」です。
「いい人」は、やさしいので、すべての人にやさしくすることがいいことだと思っています。
でも、そうではないのです。
あなたのエネルギーを奪っていくような人や、
あなたをなめてかかるような人にまで、やさしくしてはいけません。
自分が嫌われないように、「ビクビクした波動」を出すこともありません。
あなたと波長の合う人とだけ、楽しくやっていけばいいのです。
実は、「いい人」こそ、成功して豊かにならなければいけないと私は思っています。
なぜなら、「いい人」のところにお金が集まれば、「いいこと」にお金を使うからです。
「ろくでもない人」のところにお金が集まれば、「ろくでもないこと」にお金を使うでしょう。
また、お金がなければ、愛する人が困ったときに、助けてあげることができません。
「お金(経済)に強くなる」ために、最初にしなければいけないことは何でしょうか?
それは、“赤字”を出さないことです。
いままで貯金をしたことがない人は、いままでより少ない金額でやりくりする工夫をして、
月に1万でも、2万でも、貯めていく。
それができれば合格です。
それだけを心がけていればいいのです。
この「マイナスをつくらないこと」は、商売や仕事をやるうえでも、もっとも大切なことです。
商売や仕事で使うお金のことを「出金」といいます。
この「出金」を、最初から、できるかぎり減らすことです。
「儲け」を出す前に、商売道具にお金をかけてしまうことは、一番やってはいけないことですからね。
『人とお金』サンマーク出版
今年10月、伊勢神宮では20年に1度の御遷宮が行なわれた。
約1300年にわたって営々と続けられている行事で、今年は62回目の式年遷宮となる。
東の御敷地から、西の御敷地に遷(うつ)られたが、
それを米座(こめくら)から、金座(かねくら)に御遷りになった、という言い伝えがあるそうだ。
米座の時代は、平和で心豊かな「精神の時代」で、金座の時代は、動乱と激動の「経済の時代」。
いよいよ、これからの時代は、精神だけでなく、
誰もが経済やお金を学ばなければならない時代に入ったようだ。
「入るを量(はか)りて出ずるを為す」という言葉がある。
収入がどれくらいあるかを計算し、それに釣り合った出費をすることを言う。
「お金の基本は、まず赤字を出さないこと」

【お金】
いい人であればあるほど、お金の勉強は必要だ。
2013年10月09日
ある所に、お金に困っている男がいました。 「日本のいい話」 魂が震える話より~
「魂が震える話」より・・・
江戸時代のお話です。
ある所に、お金に困っている男がいました。
どうしてもお金に困っていたので、
親友の男に貸してもらおうと、意を決してその親友の家に行きました。
しかしいざ行ってみると、中々お金のことを言い出せずに時間だけが過ぎました。
帰り際、とうとう「お金を貸してくれ」と言えなかった男は、親友の家を出ます。
すると、家の中から男が出てきてこう言いました。
「夜もふけ、今日は寒いから、これを着ていきな」
「いやいや、これぐらいの寒さは大丈夫だよ」
「いいから着て帰れって」
そう言って上着を持たせてくれました。
帰り道、寒くて上着の袖に手を入れると、
そこにはお金が入っていました。
上着の暖かさと、人の温かさに、ハラハラと涙が流れました。
わたくしも、この方の様に、
言葉(話)を聞かずとも、感じ取れる人になりたい
江戸時代のお話です。
ある所に、お金に困っている男がいました。
どうしてもお金に困っていたので、
親友の男に貸してもらおうと、意を決してその親友の家に行きました。
しかしいざ行ってみると、中々お金のことを言い出せずに時間だけが過ぎました。
帰り際、とうとう「お金を貸してくれ」と言えなかった男は、親友の家を出ます。
すると、家の中から男が出てきてこう言いました。
「夜もふけ、今日は寒いから、これを着ていきな」
「いやいや、これぐらいの寒さは大丈夫だよ」
「いいから着て帰れって」
そう言って上着を持たせてくれました。
帰り道、寒くて上着の袖に手を入れると、
そこにはお金が入っていました。
上着の暖かさと、人の温かさに、ハラハラと涙が流れました。
わたくしも、この方の様に、
言葉(話)を聞かずとも、感じ取れる人になりたい

2013年09月27日
「ならぬものはならぬ」~ 如何に子供の頃から教育が大事か! 日本のいい話
【人の心に灯をともす】より~
星亮一氏の心に響く言葉より…
会津藩の子供は6歳から勉強を始める。
午前中は近所の寺子屋で論語や大学などの素読を習い、
いったん家に戻り、午後、一ヶ所に集まって、組の仲間と遊ぶのである。
一人で遊ぶことは禁止だった。
孤独な少年は皆無だった。
仲間は十人一組を意味する「什(じゅう)」と呼ばれ、年長者が什長に選ばれた。
遊びの集会場は什の家が交替で務めた。
什には掟があり、全員が集まると、そろって八つの格言を唱和した。
一、年長者の言うことを聞かなければなりませぬ。
一、年長者にお辞儀をしなければなりませぬ。
一、嘘言(うそ)をいうてはなりませぬ。
一、卑怯(ひきょう)なふるまいをしてはなりませぬ。
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ。
一、戸外で物を食べてはなりませぬ。
一、戸外で婦人と言葉を交わしてはなりませぬ。
そして最後に、
「ならぬことはならぬものです」
と唱和した。
遊びの什は各家が交替で子供たちの面倒をみたが、
菓子や果物などの間食を与えることはなかった。
夏ならば水、冬はお湯と決まっていて、そのほかは一切、出さなかった。
唱和が終わると、外に出て汗だくになって遊んだ。
普通の子供と特にかわりはなく、
駆けっこ、鬼ごっこ、相撲、雪合戦、氷すべり、樽ころがし、なんでもあった。
このようにして六歳から八歳までの子供が二年間、什で学びかつ遊ぶことで、
仲間意識が芽生え、年長者への配慮、年下の子供に対する気配りも身についた。
当然、子供の間には喧嘩や口論、掟を破ることも多々あった。
その場合、罰則が課せられたが、罰則はたとえ門閥の子供でも平等で、
家老の嫡男であろうが、十石二人扶持の次三男であっても権利は同じだった。
門閥の子供はここで仲間の大事さに目覚め、
門閥以外の子供は無批判で上士に盲従する卑屈な根性を改めることができた。
「ならぬことはならぬ」
という短い言葉は、身分や上下関係を超えた深い意味が存在した。
会津の子供たちは、こうして秩序を学び、武士道の習練を積んでいった。
教育がいかに大事かよくわかる。
それをいかに手間隙かけて、大人たちが行なっていたかである。
家庭教育と学校、そして地域社会が一体となって教育に当たった。
『会津武士道 「ならぬことはならぬ」の教え』青春出版社
子どもの教育は大事だ。
何年か先の国家の勢いや品格が決まってしまう。
「規律」、「我慢」、「気骨」、「気配り」、「敬う」、「恥(はじ)」、「卑怯(ひきょう)」
といった徳目は、「ならぬことはならぬ」という子どもの頃からの教育から生まれる。
両親や年長者を「敬う」、ということは、
幼少の頃からの「挨拶」や「礼儀」や「躾(しつけ)」より生まれる。
そのことは、
家族を愛し、地域や学校や会社などを愛し、国を愛するという大事な徳目にも通じる。
昨今は、我慢できない子供や大人も多いが、これも豊かさゆえの反動。
子どもの頃なんでも与えることによって甘やかし、我慢の教育が足りなかったからだ。
武士の行動基準は、「恥」という一語に帰結する。
しかし、「恥」という言葉が家庭で言われなくなって久しい。
恥とは、「卑怯者」であるとか「腰抜け」ということ。
名前を名乗らないというのも卑怯の最たるものだった。
陰湿なイジメなどは、もっとも恥ずべき卑怯者のすること。
「ならぬものはならぬ」という教育が今一度必要とされている。
わたくしも、古き良きものを取り入れて、今後の子育てに生かしていきたい!
星亮一氏の心に響く言葉より…
会津藩の子供は6歳から勉強を始める。
午前中は近所の寺子屋で論語や大学などの素読を習い、
いったん家に戻り、午後、一ヶ所に集まって、組の仲間と遊ぶのである。
一人で遊ぶことは禁止だった。
孤独な少年は皆無だった。
仲間は十人一組を意味する「什(じゅう)」と呼ばれ、年長者が什長に選ばれた。
遊びの集会場は什の家が交替で務めた。
什には掟があり、全員が集まると、そろって八つの格言を唱和した。
一、年長者の言うことを聞かなければなりませぬ。
一、年長者にお辞儀をしなければなりませぬ。
一、嘘言(うそ)をいうてはなりませぬ。
一、卑怯(ひきょう)なふるまいをしてはなりませぬ。
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ。
一、戸外で物を食べてはなりませぬ。
一、戸外で婦人と言葉を交わしてはなりませぬ。
そして最後に、
「ならぬことはならぬものです」
と唱和した。
遊びの什は各家が交替で子供たちの面倒をみたが、
菓子や果物などの間食を与えることはなかった。
夏ならば水、冬はお湯と決まっていて、そのほかは一切、出さなかった。
唱和が終わると、外に出て汗だくになって遊んだ。
普通の子供と特にかわりはなく、
駆けっこ、鬼ごっこ、相撲、雪合戦、氷すべり、樽ころがし、なんでもあった。
このようにして六歳から八歳までの子供が二年間、什で学びかつ遊ぶことで、
仲間意識が芽生え、年長者への配慮、年下の子供に対する気配りも身についた。
当然、子供の間には喧嘩や口論、掟を破ることも多々あった。
その場合、罰則が課せられたが、罰則はたとえ門閥の子供でも平等で、
家老の嫡男であろうが、十石二人扶持の次三男であっても権利は同じだった。
門閥の子供はここで仲間の大事さに目覚め、
門閥以外の子供は無批判で上士に盲従する卑屈な根性を改めることができた。
「ならぬことはならぬ」
という短い言葉は、身分や上下関係を超えた深い意味が存在した。
会津の子供たちは、こうして秩序を学び、武士道の習練を積んでいった。
教育がいかに大事かよくわかる。
それをいかに手間隙かけて、大人たちが行なっていたかである。
家庭教育と学校、そして地域社会が一体となって教育に当たった。
『会津武士道 「ならぬことはならぬ」の教え』青春出版社
子どもの教育は大事だ。
何年か先の国家の勢いや品格が決まってしまう。
「規律」、「我慢」、「気骨」、「気配り」、「敬う」、「恥(はじ)」、「卑怯(ひきょう)」
といった徳目は、「ならぬことはならぬ」という子どもの頃からの教育から生まれる。
両親や年長者を「敬う」、ということは、
幼少の頃からの「挨拶」や「礼儀」や「躾(しつけ)」より生まれる。
そのことは、
家族を愛し、地域や学校や会社などを愛し、国を愛するという大事な徳目にも通じる。
昨今は、我慢できない子供や大人も多いが、これも豊かさゆえの反動。
子どもの頃なんでも与えることによって甘やかし、我慢の教育が足りなかったからだ。
武士の行動基準は、「恥」という一語に帰結する。
しかし、「恥」という言葉が家庭で言われなくなって久しい。
恥とは、「卑怯者」であるとか「腰抜け」ということ。
名前を名乗らないというのも卑怯の最たるものだった。
陰湿なイジメなどは、もっとも恥ずべき卑怯者のすること。
「ならぬものはならぬ」という教育が今一度必要とされている。
わたくしも、古き良きものを取り入れて、今後の子育てに生かしていきたい!
2013年09月23日
みっともない人・・・ 「見とうもない、見たくもない人」から運が良くなる人になる秘訣~
清水祐尭氏の心に響く言葉より…
ある日、ふと気づいたのです。
運が良くなる秘訣というものが“ある!”と。
しかも、それは「特別な秘策」などではなく、むしろ何気ない毎日の行い、
「作法」とその人を取り巻くエネルギーによって決まってしまう、
ということがわかってきたのです。
運の悪い人に限って、何も意識せずに悪い作法をくり返し、
ますますエネルギー状態を悪くしていることが多いのです。
それでは、わざわざ悪運を招いているようなものです。
逆に、運のいい人は、ふだんから良い作法をくり返しているため、
エネルギーの状態が良く、「ツイてる人」になるというわけです。
たとえば、
通勤電車の中でお化粧をしたり、おにぎりやパンを食べたり、
道ばたやコンビニエンスストアの店先に座り込んだり。
近年、公共の場でのマナーというものが、
すっかり忘れられているように思われて残念です。
なぜなら、そんなことで運気を下げている人が、ほんとうに多いからです。
かつては、公衆の面前での振舞いには、親のしつけが表れると言われていました。
親は子どもに「みっともないことをするんじゃないよ!」といって、厳しくしつけたものです。
「みっともないこと」とは、「見とうもない」、つまり、「見たくもない」ということ。
見たくもないことをしている人というのは、周囲の人からの反感を買います。
見たくもないことを見せられているのですから、不快に思って当然ですよね。
つまり、不快感を抱いた周囲の人によるマイナスエネルギーを、
それこそシャワーのように浴びているようなものなのです。
「みっともない」ことは運気を下げるのです。
『風水・占いよりすごい! 開運の作法』現代書林
周囲の人たちの反感を買うことを平気でする人がいる。
たとえば、食堂やショップで、
ささいなことで大声で怒鳴ったり、クレームをつける人たちだ。
その場は、一瞬にして空気が凍りついたようになってしまう。
場のエネルギーが瞬間的に落ちるからだ。
それこそが「見とうもない」瞬間であり、「みっともない」こと。
周りの人たちの気分を悪くすることは、負のエネルギーを集めること。
その反対に、その人が入ってきた瞬間に皆が明るくなり、笑顔になるなら、
その人はプラスのエネルギーを発し、同時にプラスのエネルギーも集めている。
みっともないことは止めて、プラスのエネルギーを集める人でありたい。

ウチの息子も、
わたくしの躾もですが、周りの方々にも躾をして頂き、
ちゃんとした振る舞いが出来る様になって欲しい
わたくしもちゃんと躾出来るよう、頑張らないといけないな
ある日、ふと気づいたのです。
運が良くなる秘訣というものが“ある!”と。
しかも、それは「特別な秘策」などではなく、むしろ何気ない毎日の行い、
「作法」とその人を取り巻くエネルギーによって決まってしまう、
ということがわかってきたのです。
運の悪い人に限って、何も意識せずに悪い作法をくり返し、
ますますエネルギー状態を悪くしていることが多いのです。
それでは、わざわざ悪運を招いているようなものです。
逆に、運のいい人は、ふだんから良い作法をくり返しているため、
エネルギーの状態が良く、「ツイてる人」になるというわけです。
たとえば、
通勤電車の中でお化粧をしたり、おにぎりやパンを食べたり、
道ばたやコンビニエンスストアの店先に座り込んだり。
近年、公共の場でのマナーというものが、
すっかり忘れられているように思われて残念です。
なぜなら、そんなことで運気を下げている人が、ほんとうに多いからです。
かつては、公衆の面前での振舞いには、親のしつけが表れると言われていました。
親は子どもに「みっともないことをするんじゃないよ!」といって、厳しくしつけたものです。
「みっともないこと」とは、「見とうもない」、つまり、「見たくもない」ということ。
見たくもないことをしている人というのは、周囲の人からの反感を買います。
見たくもないことを見せられているのですから、不快に思って当然ですよね。
つまり、不快感を抱いた周囲の人によるマイナスエネルギーを、
それこそシャワーのように浴びているようなものなのです。
「みっともない」ことは運気を下げるのです。
『風水・占いよりすごい! 開運の作法』現代書林
周囲の人たちの反感を買うことを平気でする人がいる。
たとえば、食堂やショップで、
ささいなことで大声で怒鳴ったり、クレームをつける人たちだ。
その場は、一瞬にして空気が凍りついたようになってしまう。
場のエネルギーが瞬間的に落ちるからだ。
それこそが「見とうもない」瞬間であり、「みっともない」こと。
周りの人たちの気分を悪くすることは、負のエネルギーを集めること。
その反対に、その人が入ってきた瞬間に皆が明るくなり、笑顔になるなら、
その人はプラスのエネルギーを発し、同時にプラスのエネルギーも集めている。
みっともないことは止めて、プラスのエネルギーを集める人でありたい。

ウチの息子も、
わたくしの躾もですが、周りの方々にも躾をして頂き、
ちゃんとした振る舞いが出来る様になって欲しい

わたくしもちゃんと躾出来るよう、頑張らないといけないな

2013年09月22日
誕生日というのは・・・ 「日本のいい話」 ウチの息子も感謝出来る人に~(^^♪
志賀内康弘氏の心に響く言葉より…
私の友人の女性のお母さんは、
たいへん面倒見の良い人で、困った人がいると放っておけない性分でした。
その人柄を頼って、いつも家には親戚や友人などが泊まっていたそうです。
ある日のこと、彼女の家に母親の知人であるカナダ人一家が泊まりに来ていました。
お母さんは彼女に、「このカナダ人一家を東京観光に連れて行ってあげなさい」と言いました。
その日は彼女の15歳の誕生日でした。
彼女は朝からワクワクしていました。
「お母さんは何をプレゼントしてくれるのだろう?」と楽しみにしていたのです。
そこへ「知人のカナダ人一家を東京観光に連れて行け」と言われたので、
彼女はむくれて出掛けました。
そんな彼女の嫌々の態度は、カナダ人家族にも伝わったようでした。
彼女は観光案内から帰ってくるなり母親に文句を言いました。
「今日は私の誕生日なのよ。なぜ、そんな日に他人の観光案内をしなくちゃいけないのよ!」
すると、いきなり母親の鉄拳が飛びました。
平手ではありません。
ゲンコツだったそうです。
そして、言いました。
「誕生日だからといって、誰かに何かをしてもらおうとか、祝ってもらおうという気持ちがダメだ。
あなたはいったい、何をしてもらおうと思っているの?
誕生日というのはね、生まれてきたこと、育ててもらったことに感謝する日なのよ」
この言葉は15歳の少女の心だけでなく、
いい歳をしたオジサンである筆者にとっても衝撃的な言葉です。
私も、「誕生日に何をもらえるか」ばかり考えて生きてきたからです。
さらに、お母さんは言います。
「何かをすることによって相手に見返りを求めてはいけない。
相手をどれだけ楽しませたり、喜ばせたりしようとする気持ちがないから不満に思うのだ。
お前は人間がちっちゃい」
彼女は、この教えを受けて育ったせいでしょう。
人を元気にする、人を喜ばせる名人です。
『他人と比べない生き方』フォーユー
松下幸之助翁は、部下が入院したとき、病院に見舞いに行き、こう言ったという。
「退院したら”病気ありがとう”という記念行事をやりや」
病気から逃げるのではなく、これも修行だと思い、
病気と仲よくしようとすると、病気の方から逃げていくのだという。
病気は、健康であることのありがたさを教えてくれる。
快気祝いは、
退院を祝ってもらうのではなく、日頃の健康や、
お世話になっている家族、周囲の人たちに感謝する日。
誕生日は、
プレゼントをもらったり、まわりに祝ってもらうのではなく、
生まれたこと、育ててもらったことに感謝する日。
感謝が生まれると、人を喜ばせることができる。

【親子写真】
ウチの息子も、
人を元気にする・人を喜ばせる人になって欲しい!
わたくしの躾が大事になるなぁ~(笑)
私の友人の女性のお母さんは、
たいへん面倒見の良い人で、困った人がいると放っておけない性分でした。
その人柄を頼って、いつも家には親戚や友人などが泊まっていたそうです。
ある日のこと、彼女の家に母親の知人であるカナダ人一家が泊まりに来ていました。
お母さんは彼女に、「このカナダ人一家を東京観光に連れて行ってあげなさい」と言いました。
その日は彼女の15歳の誕生日でした。
彼女は朝からワクワクしていました。
「お母さんは何をプレゼントしてくれるのだろう?」と楽しみにしていたのです。
そこへ「知人のカナダ人一家を東京観光に連れて行け」と言われたので、
彼女はむくれて出掛けました。
そんな彼女の嫌々の態度は、カナダ人家族にも伝わったようでした。
彼女は観光案内から帰ってくるなり母親に文句を言いました。
「今日は私の誕生日なのよ。なぜ、そんな日に他人の観光案内をしなくちゃいけないのよ!」
すると、いきなり母親の鉄拳が飛びました。
平手ではありません。
ゲンコツだったそうです。
そして、言いました。
「誕生日だからといって、誰かに何かをしてもらおうとか、祝ってもらおうという気持ちがダメだ。
あなたはいったい、何をしてもらおうと思っているの?
誕生日というのはね、生まれてきたこと、育ててもらったことに感謝する日なのよ」
この言葉は15歳の少女の心だけでなく、
いい歳をしたオジサンである筆者にとっても衝撃的な言葉です。
私も、「誕生日に何をもらえるか」ばかり考えて生きてきたからです。
さらに、お母さんは言います。
「何かをすることによって相手に見返りを求めてはいけない。
相手をどれだけ楽しませたり、喜ばせたりしようとする気持ちがないから不満に思うのだ。
お前は人間がちっちゃい」
彼女は、この教えを受けて育ったせいでしょう。
人を元気にする、人を喜ばせる名人です。
『他人と比べない生き方』フォーユー
松下幸之助翁は、部下が入院したとき、病院に見舞いに行き、こう言ったという。
「退院したら”病気ありがとう”という記念行事をやりや」
病気から逃げるのではなく、これも修行だと思い、
病気と仲よくしようとすると、病気の方から逃げていくのだという。
病気は、健康であることのありがたさを教えてくれる。
快気祝いは、
退院を祝ってもらうのではなく、日頃の健康や、
お世話になっている家族、周囲の人たちに感謝する日。
誕生日は、
プレゼントをもらったり、まわりに祝ってもらうのではなく、
生まれたこと、育ててもらったことに感謝する日。
感謝が生まれると、人を喜ばせることができる。

【親子写真】
ウチの息子も、
人を元気にする・人を喜ばせる人になって欲しい!
わたくしの躾が大事になるなぁ~(笑)
2013年08月29日
「先縁尊重」~ 人生で忘れてはいけない、とても大切な事!
致知出版、藤尾秀昭氏の心に響く言葉より…
「人生で大事なものは何か」
たくさんの人たちの答えを一語に集約すると、
「先縁尊重(せんえんそんちょう)」という言葉に表現できると思います。
原点の人を忘れないで大事にするということです。
例えばAさんからBさんを紹介され、Bさんと大変親しくなり、Aさんを忘れてしまう。
挙げ句は無視したり、不義理をする。
そういう原点の人を大事にしない人は運命から見放されてしまう、ということです。
私の知っている経営者にこういう方がいます。
その人は丁稚(でっち)奉公に入った店の主人から、
ある日突然、理不尽に解雇されたにもかかわらず、
毎年正月に、その元主人の家に年始の挨拶に行くことを欠かさなかった、といいます。
普通なら恨みに思っても不思議はないところですが、
自分がこうして曲がりなりにも商いをやっているのは、
その元主人が自分に仕事を教えてくれたおかげだという原点を忘れなかったのです。
この人はまさに先縁尊重を実戦した人です。
この人の会社が創業44年、なおも隆盛しているのは、この精神と無縁ではないと思います。
先縁の原点は親です。
親がいなければ、私たちは誰一人この世に存在していません。
その親を大事にしない人は、やはり運命が発展していきません。
親は、いわば根っこですね。
根っこに水をやらなければ、あらゆる植物は枯れてしまいます。
親を大事にするというのは、根っこに水をやるのと同じです。
「父母の恩の有無厚薄を問わない。父母即恩である」
と西晋一郎先生はいっています。
まさに至言です。
この覚悟のもとに立つ時、人生に真の主体が立つのだと思います。
そして、その親の恩をさらにさかのぼってゆくと、国というものに行きつきます。
この国のあることによって、私たち祖先はその生命を維持継承してきたのです。
即ち、国恩です。
国恩あることによって、私たちはいまここに、生きています。
最近はこの“国の恩”ということを意識する人が少なくなりました。
そういう国民は発展しないと思います。
いま日本に確たるものがなく、漂流しているがごとき感があることと、
国恩という言葉も意識も薄れていることとは無縁ではないと思います。
『生きる力になる言葉』致知出版社
中国の「大学」の中に、
「物に本末(ほんまつ)有り。
事に終始(しゅうし)有り。
先後(せんご)する所を知れば、則(すなわ)ち道に近し」の一文がある。
物には「本(もと)」と「末(すえ)」があるということ。
事には始めと終わりがある、ということ。
何が本で、何が末か。
何が始めで、何が終わり(最後)か。
その順序を間違えると、あらゆる事はスムーズに運びませんよ、ということです。
(以上、同書より)
我々は本という原点忘れてしまうと、常に右往左往しなければいけない。
「木を見て森を見ず」のように、枝葉を見て、本質を見ようとしないからだ。
どんな事象にも根っこはある。
それが「先縁」という最初に結んだ縁。
歌にもあるように、「義理が廃(すた)ればこの世は闇」だ。
人の縁、親の縁、国の縁…
すべての「先縁」を大事にしたい。

生きていく上で、「人・親。国の縁」て本当に大事ですよね
それに、ブログでの縁もですね
「人生で大事なものは何か」
たくさんの人たちの答えを一語に集約すると、
「先縁尊重(せんえんそんちょう)」という言葉に表現できると思います。
原点の人を忘れないで大事にするということです。
例えばAさんからBさんを紹介され、Bさんと大変親しくなり、Aさんを忘れてしまう。
挙げ句は無視したり、不義理をする。
そういう原点の人を大事にしない人は運命から見放されてしまう、ということです。
私の知っている経営者にこういう方がいます。
その人は丁稚(でっち)奉公に入った店の主人から、
ある日突然、理不尽に解雇されたにもかかわらず、
毎年正月に、その元主人の家に年始の挨拶に行くことを欠かさなかった、といいます。
普通なら恨みに思っても不思議はないところですが、
自分がこうして曲がりなりにも商いをやっているのは、
その元主人が自分に仕事を教えてくれたおかげだという原点を忘れなかったのです。
この人はまさに先縁尊重を実戦した人です。
この人の会社が創業44年、なおも隆盛しているのは、この精神と無縁ではないと思います。
先縁の原点は親です。
親がいなければ、私たちは誰一人この世に存在していません。
その親を大事にしない人は、やはり運命が発展していきません。
親は、いわば根っこですね。
根っこに水をやらなければ、あらゆる植物は枯れてしまいます。
親を大事にするというのは、根っこに水をやるのと同じです。
「父母の恩の有無厚薄を問わない。父母即恩である」
と西晋一郎先生はいっています。
まさに至言です。
この覚悟のもとに立つ時、人生に真の主体が立つのだと思います。
そして、その親の恩をさらにさかのぼってゆくと、国というものに行きつきます。
この国のあることによって、私たち祖先はその生命を維持継承してきたのです。
即ち、国恩です。
国恩あることによって、私たちはいまここに、生きています。
最近はこの“国の恩”ということを意識する人が少なくなりました。
そういう国民は発展しないと思います。
いま日本に確たるものがなく、漂流しているがごとき感があることと、
国恩という言葉も意識も薄れていることとは無縁ではないと思います。
『生きる力になる言葉』致知出版社
中国の「大学」の中に、
「物に本末(ほんまつ)有り。
事に終始(しゅうし)有り。
先後(せんご)する所を知れば、則(すなわ)ち道に近し」の一文がある。
物には「本(もと)」と「末(すえ)」があるということ。
事には始めと終わりがある、ということ。
何が本で、何が末か。
何が始めで、何が終わり(最後)か。
その順序を間違えると、あらゆる事はスムーズに運びませんよ、ということです。
(以上、同書より)
我々は本という原点忘れてしまうと、常に右往左往しなければいけない。
「木を見て森を見ず」のように、枝葉を見て、本質を見ようとしないからだ。
どんな事象にも根っこはある。
それが「先縁」という最初に結んだ縁。
歌にもあるように、「義理が廃(すた)ればこの世は闇」だ。
人の縁、親の縁、国の縁…
すべての「先縁」を大事にしたい。

生きていく上で、「人・親。国の縁」て本当に大事ですよね

それに、ブログでの縁もですね

2013年07月16日
誰がやっても、どんな場合でも通用し、人生の成功者になる為の法則~ 「感謝」!
【人の心に灯をともす】
http://merumo.ne.jp/00564226.html
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
■
「お互いわかっているから、『ありがとう』『感謝してます』って言わなくてもいいんだ」
ではないのです。
お互いわかっているのに、言いあわないから、血みどろの戦いになるのです。
もっと、幸せになりたかったら、お互い感謝してください。
■
「感謝してます」
といえば、その問題は終わるんです。
でも、最初から問題そのものに感謝するという流れには行かないものなのです。
だから、最初は問題を起こしていないまわりに感謝から始めるのです。
まわりへの感謝から始めると、やがて、その問題にも感謝できるようになります。
そして、魂が上にあがります。
■
「感謝」の法則は、誰がやっても、どんな場合でも絶対通用します。
そして、感謝で魂は向上すると同時に、問題が解決することになっています。
運命が好転するようになっています。
■
もちろん、「ありがとう」といってもいいですよ。
ただ、「感謝してます」の波動が100点だとしたら、「ありがとう」の波動は50点ぐらいです。
高い波動のある言葉だから、これを使ったほうがいいですよ。
■
会社へ行っても、そうですよ。
給料日に、当然という顔をして給料をもらっている人もいるけれど、社長さんに、
「ありがとうございます」
「感謝してます」
って言ってごらん。
この一言を言えるか否かで、人生、えらく違ってきますよ。
■
この世で人生の成功者になるには、ただ一点、感謝です。
逆をいうと、「当たり前」といった瞬間から、不幸が始まる。
『斎藤一人 仕事がうまくいく315のチカラ』KKロングセラーズ
本当は、世の中の全てのことは、当たり前のことなど一つもない。
日本に生まれたことも、息ができることも、食事をいただけることも、そして今この世に生まれたことも…
ありえないくらい不思議なことだから、「有り難し」という。
「当たり前」と思った瞬間から、傲慢になり、感謝がなくなる。
どんなときにも、「感謝してます」と言う習慣を身につけたい。

今日も一日、健康で過ごす事が出来、感謝
暑い日が続いています。
皆様、熱中症に気をつけましょう
http://merumo.ne.jp/00564226.html
斎藤一人さんの心に響く言葉より…
■
「お互いわかっているから、『ありがとう』『感謝してます』って言わなくてもいいんだ」
ではないのです。
お互いわかっているのに、言いあわないから、血みどろの戦いになるのです。
もっと、幸せになりたかったら、お互い感謝してください。
■
「感謝してます」
といえば、その問題は終わるんです。
でも、最初から問題そのものに感謝するという流れには行かないものなのです。
だから、最初は問題を起こしていないまわりに感謝から始めるのです。
まわりへの感謝から始めると、やがて、その問題にも感謝できるようになります。
そして、魂が上にあがります。
■
「感謝」の法則は、誰がやっても、どんな場合でも絶対通用します。
そして、感謝で魂は向上すると同時に、問題が解決することになっています。
運命が好転するようになっています。
■
もちろん、「ありがとう」といってもいいですよ。
ただ、「感謝してます」の波動が100点だとしたら、「ありがとう」の波動は50点ぐらいです。
高い波動のある言葉だから、これを使ったほうがいいですよ。
■
会社へ行っても、そうですよ。
給料日に、当然という顔をして給料をもらっている人もいるけれど、社長さんに、
「ありがとうございます」
「感謝してます」
って言ってごらん。
この一言を言えるか否かで、人生、えらく違ってきますよ。
■
この世で人生の成功者になるには、ただ一点、感謝です。
逆をいうと、「当たり前」といった瞬間から、不幸が始まる。
『斎藤一人 仕事がうまくいく315のチカラ』KKロングセラーズ
本当は、世の中の全てのことは、当たり前のことなど一つもない。
日本に生まれたことも、息ができることも、食事をいただけることも、そして今この世に生まれたことも…
ありえないくらい不思議なことだから、「有り難し」という。
「当たり前」と思った瞬間から、傲慢になり、感謝がなくなる。
どんなときにも、「感謝してます」と言う習慣を身につけたい。

今日も一日、健康で過ごす事が出来、感謝

暑い日が続いています。
皆様、熱中症に気をつけましょう

2013年05月27日
今回も良い刺激になった福岡での交流会~ 第32回 生涯教育実践研究交流会
先週(19日)、福岡で行われた~
第32回 中国・四国・九州地区 生涯教育実践研究交流会に参加して来ました。

【福岡県立社会教育総合センター 畳屋息子】
特別企画 インタビュー・ダイアローグ
1部~幼児期の教育プログラムについて~
「【鍛える】幼稚園・保育園に問う。ー今なぜ幼児鍛錬なのか?ー」
登壇者~
浜田 満明 園長(島根県出雲市立 高浜幼稚園)
矢野 やす子 園長(鹿児島県志布志市 伊崎田保育園)
コーディネーター~
大島 まな 准教授(九州女子大学)

【左 大島先生 中 浜田園長 右 矢野園長】
わたくし、1部の企画がとても興味がありました。
ヨコミネ式保育の伊崎田園長さんのお話が聞けたので、参加出来て良かったです。
(興味がありましたので、以前、たちばな保育園にお邪魔した事があります。)
園長が信念を持って行動された結果、どちらも評価を得ている保育・幼稚園になっています。
素晴らしいお話が聞けて良かったです
2部~高齢者の社会参画を考える~
「高齢研究者に問う。2020年の【高齢者爆発】をどう回避すべきか?」
登壇者~
三浦 清一郎さん(月刊生涯学習通信「風の便り」 編集・発行人)
瀬沼 克彰(よしあき)さん(桜美林大学 名誉教授)
コーディネーター~
森本 精造さん(NPO法人幼老共生まちづくり支援協会 理事長)

【左 森本理事長 中 瀬沼名誉教授 右 三浦先生】
退職した後、どう過ごすのか!
まだ先の話ですが、考えておかなければならない事だと・・・
健康でいて、社会貢献が出来る様にしておかなければと思いました!
日曜日だけの参加でしたが、とても勉強になりました。
以前、30回大会に参加したですが、
当時の事は、実践発表会記事 交流会・特別企画記事を、ご覧になって見て下さい
今回も、三浦清一郎先生の本を購入して来ました

【三浦 清一郎先生の本】
先生にお願いをしたら、心良く書いてくださいました

【三浦先生のサイン】
先生の本を読む事もですし、
まだ読んでない本もありますので、
2週間程、勉強の時間に当てたいと思います。
なので・・・
しばらく、ブログはお休み致します。
いつも拝見して頂いてる皆様、ありがとうございます(_ _)
また、数週間後に宜しくお願い致します
第32回 中国・四国・九州地区 生涯教育実践研究交流会に参加して来ました。

【福岡県立社会教育総合センター 畳屋息子】
特別企画 インタビュー・ダイアローグ
1部~幼児期の教育プログラムについて~
「【鍛える】幼稚園・保育園に問う。ー今なぜ幼児鍛錬なのか?ー」
登壇者~
浜田 満明 園長(島根県出雲市立 高浜幼稚園)
矢野 やす子 園長(鹿児島県志布志市 伊崎田保育園)
コーディネーター~
大島 まな 准教授(九州女子大学)

【左 大島先生 中 浜田園長 右 矢野園長】
わたくし、1部の企画がとても興味がありました。
ヨコミネ式保育の伊崎田園長さんのお話が聞けたので、参加出来て良かったです。
(興味がありましたので、以前、たちばな保育園にお邪魔した事があります。)
園長が信念を持って行動された結果、どちらも評価を得ている保育・幼稚園になっています。
素晴らしいお話が聞けて良かったです

2部~高齢者の社会参画を考える~
「高齢研究者に問う。2020年の【高齢者爆発】をどう回避すべきか?」
登壇者~
三浦 清一郎さん(月刊生涯学習通信「風の便り」 編集・発行人)
瀬沼 克彰(よしあき)さん(桜美林大学 名誉教授)
コーディネーター~
森本 精造さん(NPO法人幼老共生まちづくり支援協会 理事長)

【左 森本理事長 中 瀬沼名誉教授 右 三浦先生】
退職した後、どう過ごすのか!
まだ先の話ですが、考えておかなければならない事だと・・・
健康でいて、社会貢献が出来る様にしておかなければと思いました!
日曜日だけの参加でしたが、とても勉強になりました。
以前、30回大会に参加したですが、
当時の事は、実践発表会記事 交流会・特別企画記事を、ご覧になって見て下さい

今回も、三浦清一郎先生の本を購入して来ました


【三浦 清一郎先生の本】
先生にお願いをしたら、心良く書いてくださいました


【三浦先生のサイン】
先生の本を読む事もですし、
まだ読んでない本もありますので、
2週間程、勉強の時間に当てたいと思います。
なので・・・
しばらく、ブログはお休み致します。
いつも拝見して頂いてる皆様、ありがとうございます(_ _)
また、数週間後に宜しくお願い致します

2013年05月26日
指摘され、毎朝している習慣~ 生きていく上でとても大事なこと。
佐藤伝氏の心に響く言葉より…
朝、出勤前に仏壇や神棚など、
ご先祖を象徴するものに手を合わせる習慣を持っていますか?
慌しく出勤するのではなく、たとえ一人暮らしでも、
「ご先祖さま、行ってまいりま~す!」と元気に声を出して出かけましょう。
人は合掌したまま怒ることができません。
ウソだと思ったら試しにやってみてください。
逆に笑ってしまいます。
それくらい合掌パワーってすごいんです。
あなたの祖先を10代さかのぼるだけで2046人のご先祖がいます。
20代では、いっきに増えて209万7150人、25代(約700年前)までさかのぼれば、
6710万8862人ものご先祖の先頭を走る代表が、あなたであることがわかります。
このうち誰か一人でもかけていたら、あなたはこの世に出現していないのです。
いま、生きていることが奇跡の存在といわれる所以(ゆえん)です。
自分の部屋に仏壇も神棚もないんだけど、という方は、さっそく神聖なコーナーを設けましょう。
ほんのちょっとのスペースでいいんです。
とにかく大事なことは、目に見えないものに感謝する姿勢です。
こんなにたくさんの目に見えないサポーターの方たちの応援を受けて、うまくいかないわけがない。
もしもうまくいっていないと感じているのなら、代表としての自覚と感謝の二つが足りないだけです。
日々、ご先祖さまに感謝と畏敬の念を忘れなければ、
強力な大応援団のバックアップを得て、あなたの幸せプロジェクトは、着々と進んでいくはずです。
『幸運を呼びよせる 朝の習慣』中経出版
生きていく上でとても大事なことは、
自分のご先祖に対して、手を合わせ感謝するという習慣。
目に見えないものに畏敬の念を持てない人は、
残念ながら表面的で底の浅い人生を過ごすしかない。
西田文郎先生は、お釈迦さまが教えた、「六方拝」をすすめている。
これは、“東西南北天地”の六方に感謝するというもの。
東を向いて両親やご先祖様に、西を向いて家族に、南を向いて恩師に、
北を向いて友人に、天地は太陽や、大地など自然のすべてに感謝をする。
感謝をすれば、自分が一人で生きているわけではなく、
周囲の人々や様々なご縁によって生かされていることに気づく。
祈りの本質は、何かをお願いすることではなく、ただただ、今あることに感謝すること。
感謝と畏敬の念を忘れない人でありたい。

わたくし、お恥ずかしい事に、
昔、ご先祖様に感謝する事を疎かにしていたのですが、
お世話になっている方に、
毎日、ご先祖様には手をお合わせて感謝をしないといけませんよと言われましたので、
今は、毎朝ご先祖様に感謝して、
家族の健康、そして、お世話になっている方の健康をお祈りしています。
朝、出勤前に仏壇や神棚など、
ご先祖を象徴するものに手を合わせる習慣を持っていますか?
慌しく出勤するのではなく、たとえ一人暮らしでも、
「ご先祖さま、行ってまいりま~す!」と元気に声を出して出かけましょう。
人は合掌したまま怒ることができません。
ウソだと思ったら試しにやってみてください。
逆に笑ってしまいます。
それくらい合掌パワーってすごいんです。
あなたの祖先を10代さかのぼるだけで2046人のご先祖がいます。
20代では、いっきに増えて209万7150人、25代(約700年前)までさかのぼれば、
6710万8862人ものご先祖の先頭を走る代表が、あなたであることがわかります。
このうち誰か一人でもかけていたら、あなたはこの世に出現していないのです。
いま、生きていることが奇跡の存在といわれる所以(ゆえん)です。
自分の部屋に仏壇も神棚もないんだけど、という方は、さっそく神聖なコーナーを設けましょう。
ほんのちょっとのスペースでいいんです。
とにかく大事なことは、目に見えないものに感謝する姿勢です。
こんなにたくさんの目に見えないサポーターの方たちの応援を受けて、うまくいかないわけがない。
もしもうまくいっていないと感じているのなら、代表としての自覚と感謝の二つが足りないだけです。
日々、ご先祖さまに感謝と畏敬の念を忘れなければ、
強力な大応援団のバックアップを得て、あなたの幸せプロジェクトは、着々と進んでいくはずです。
『幸運を呼びよせる 朝の習慣』中経出版
生きていく上でとても大事なことは、
自分のご先祖に対して、手を合わせ感謝するという習慣。
目に見えないものに畏敬の念を持てない人は、
残念ながら表面的で底の浅い人生を過ごすしかない。
西田文郎先生は、お釈迦さまが教えた、「六方拝」をすすめている。
これは、“東西南北天地”の六方に感謝するというもの。
東を向いて両親やご先祖様に、西を向いて家族に、南を向いて恩師に、
北を向いて友人に、天地は太陽や、大地など自然のすべてに感謝をする。
感謝をすれば、自分が一人で生きているわけではなく、
周囲の人々や様々なご縁によって生かされていることに気づく。
祈りの本質は、何かをお願いすることではなく、ただただ、今あることに感謝すること。
感謝と畏敬の念を忘れない人でありたい。

わたくし、お恥ずかしい事に、
昔、ご先祖様に感謝する事を疎かにしていたのですが、
お世話になっている方に、
毎日、ご先祖様には手をお合わせて感謝をしないといけませんよと言われましたので、
今は、毎朝ご先祖様に感謝して、
家族の健康、そして、お世話になっている方の健康をお祈りしています。
2013年05月25日
いかにして全国的なブームを巻き起こしたのか!
食材の素材のうまみを引き出す発酵調味料として、
いま全国的なブームになっている「塩糀(しおこうじ)」。
この火付け役が、大分県で三百二十年間続く「糀屋本店」の浅利妙峰さんです。
時代とともに糀への需要が減り続けてきた中、いかにしてこのブームを巻き起こしたのでしょうか。
致知2013年6月号特集「一灯照隅」より
浅利妙峰さんの言葉
【記者:塩糀を現代の料理にアレンジされたところも、広く受け入れられた要因の一つでしょうね】
私は「温故知新」という言葉が好きなのですが、
真理というものは何千年も何万年も前から変わらず未来永劫に存している。
それをどう磨き出すかは現代に生きる私たちに委ねられています。
糀は日本の食文化の根幹にありますが、
味噌や醤油をもう一度各家庭で手づくりしましょう、というのは無理があります。
味噌や醤油は1年かかりますからね。
でも、塩糀は1週間あればつくれます。
簡単で、しかも料理はおいしい。
そういう点も、塩糀が現代社会のニーズに合っているところだと思います。
【記者:塩糀を蘇らせた立役者ですが、浅利さんは商標権を一切取らなかったそうですね】
熱心に勧めてくれる人もあったのですが、
何もエジソンが電球をつくったような大発明ではなく、
たまたま文献の中から見つけ使い方をアレンジしただけ、
「塩糀」はもともと日本の食文化の中にあったものです。
また、糀菌が育つのは自然の作用です。
私たちも作り手として懸命に関わっています。
糀は人智を超えた力でつくられるもので、それを1人の人間が勝手に取り扱うべきではないと。
現実的に考えても、うち1軒だけではここまで広がらなかったでしょう。
大手の食品メーカーさんが参入されたから日本中に浸透し、定着したと思います。
「奪い合えば足りず、分かち合えば余る」
といいますが、1人勝ちしようとすると、絶対に長続きしません。
【記者:いま全国の糀屋さんを訪ねて料理教室を開催し、応援しているのも、そういうお考えからですか】
そうです。
また、長い歴史の中で、うちの先祖が助けられたこともあるでしょうし、
まだ見ぬ未来の子孫がどなたかに助けられるかもしれない。
お互い助け合う中で生きている。
情けは人のためならずの言葉のとおり、
善の種を蒔けば、どこかで善の花が咲くことを信じていますし、実践しています。

【なずな庵さんの塩糀料理】
いま全国的なブームになっている「塩糀(しおこうじ)」。
この火付け役が、大分県で三百二十年間続く「糀屋本店」の浅利妙峰さんです。
時代とともに糀への需要が減り続けてきた中、いかにしてこのブームを巻き起こしたのでしょうか。
致知2013年6月号特集「一灯照隅」より
浅利妙峰さんの言葉
【記者:塩糀を現代の料理にアレンジされたところも、広く受け入れられた要因の一つでしょうね】
私は「温故知新」という言葉が好きなのですが、
真理というものは何千年も何万年も前から変わらず未来永劫に存している。
それをどう磨き出すかは現代に生きる私たちに委ねられています。
糀は日本の食文化の根幹にありますが、
味噌や醤油をもう一度各家庭で手づくりしましょう、というのは無理があります。
味噌や醤油は1年かかりますからね。
でも、塩糀は1週間あればつくれます。
簡単で、しかも料理はおいしい。
そういう点も、塩糀が現代社会のニーズに合っているところだと思います。
【記者:塩糀を蘇らせた立役者ですが、浅利さんは商標権を一切取らなかったそうですね】
熱心に勧めてくれる人もあったのですが、
何もエジソンが電球をつくったような大発明ではなく、
たまたま文献の中から見つけ使い方をアレンジしただけ、
「塩糀」はもともと日本の食文化の中にあったものです。
また、糀菌が育つのは自然の作用です。
私たちも作り手として懸命に関わっています。
糀は人智を超えた力でつくられるもので、それを1人の人間が勝手に取り扱うべきではないと。
現実的に考えても、うち1軒だけではここまで広がらなかったでしょう。
大手の食品メーカーさんが参入されたから日本中に浸透し、定着したと思います。
「奪い合えば足りず、分かち合えば余る」
といいますが、1人勝ちしようとすると、絶対に長続きしません。
【記者:いま全国の糀屋さんを訪ねて料理教室を開催し、応援しているのも、そういうお考えからですか】
そうです。
また、長い歴史の中で、うちの先祖が助けられたこともあるでしょうし、
まだ見ぬ未来の子孫がどなたかに助けられるかもしれない。
お互い助け合う中で生きている。
情けは人のためならずの言葉のとおり、
善の種を蒔けば、どこかで善の花が咲くことを信じていますし、実践しています。

【なずな庵さんの塩糀料理】
2013年05月20日
簡単な事のようですが難しい事~ 日々、心がけたい事ですね(^-^)
中山和義氏の心に響く言葉より…
デパートで働いているある女性は、いつも先輩に、
「もっと楽しそうに仕事をしなさい。
そんな疲れた顔でお客さんの相手をしたら誰も買ってくれないわよ」と怒られていました。
彼女もそのことはわかっていたのですが、
仕事が嫌になっていたので、それがどうしても顔や態度に表れてしまっていました。
ある日、彼女はAさんと一緒に催事の販売をすることになりました。
Aさんは彼女の同僚で、いつも本当に楽しそうに働いている女性です。
Aさんは、慣れていない忙しい催事の現場でも、いつものように笑顔で働いていました。
どうしてそんなにいつも笑顔でいられるのだろうと思った彼女は、思いきってAさんに、
「どうして、そんなにいつも楽しそうに仕事をしているんですか?」と尋ねてみました。
Aさんは、
「そんなに楽しそうに仕事をしているように見えますか?
そうだとしたらそれは亡くなった私の母のおかげだと思います」と答えました。
その日の仕事が終った後、彼女はAさんからお母さんの話を詳しく聞きました。
Aさんは、お父さんが病気で小さい頃に亡くなってしまったため、お母さんに育てられたそうです。
お母さんは、仕事でどんなに疲れて帰ってきても、いつもAさんの前では笑顔でいたそうです。
ある日、Aさんが、
「どうして、お母さんはいつも楽しそうなの?
疲れたりしないの?」
と尋ねると、お母さんは、
「お母さんだって疲れているときや嫌な気分のときもあるよ。
でも、そんなときこそ、笑顔でいないといけないと思っているの。
ためしに笑顔を作ってごらん。
楽しい気分になるでしょ」と答えました。
Aさんがお母さんに言われた通りに笑顔を作ると、お母さんは、
「その笑顔を見たいから、お母さんはいつも笑顔でいるんだよ」
と微笑みながら話してくれたそうです。
最後にAさんは、彼女に向かって笑顔で言いました。
「家は貧乏で大変でしたが、母の笑顔のおかげでいつも楽しかったんです。
楽しいから笑顔でいるのではなくて、笑顔でいるから楽しくなるんですよ」
次の日、彼女はAさんのように朝から笑顔でいるように気をつけました。
すると、いつもはあまり話しかけてくれない人まで、
「おはよう、楽しそうだね」とか、
「今日はやけに機嫌がいいね」などと話しかけてくれました。
彼女の気持ちも自然に楽しくなりました。
笑顔の人の周りには、笑顔の人が集まってきます、だから、楽しいことも増えていくのです。
『会社に行くのがもっと楽しみになる感動の21話』三笠書房
「悲しいから泣くのではない、泣くから悲しいのだ」
という心理学の有名な言葉がある。
つまり、身体的な反応を意図的に起こせば、後からその感情がついてくるということ。
それは、楽しいという感情も同じ。
「楽しいから笑顔でいるのではない、笑顔でいるから楽しくなるのだ」
いつも不機嫌で、怒ったような顔をしていれば、
不平不満、文句や愚痴ばかり言う嫌なヤツになる。
人は、その表情や態度に似合った人になる。
いつも笑顔で機嫌よくしている人は、幸せを引き寄せる。

簡単な事のようですが難しい事ですよね~
その日の体調などに影響しますからね。
相手の表情や態度で、こちらもそうなりますよね。
今日も、皆様が笑顔で過ごせる一日になりますように
デパートで働いているある女性は、いつも先輩に、
「もっと楽しそうに仕事をしなさい。
そんな疲れた顔でお客さんの相手をしたら誰も買ってくれないわよ」と怒られていました。
彼女もそのことはわかっていたのですが、
仕事が嫌になっていたので、それがどうしても顔や態度に表れてしまっていました。
ある日、彼女はAさんと一緒に催事の販売をすることになりました。
Aさんは彼女の同僚で、いつも本当に楽しそうに働いている女性です。
Aさんは、慣れていない忙しい催事の現場でも、いつものように笑顔で働いていました。
どうしてそんなにいつも笑顔でいられるのだろうと思った彼女は、思いきってAさんに、
「どうして、そんなにいつも楽しそうに仕事をしているんですか?」と尋ねてみました。
Aさんは、
「そんなに楽しそうに仕事をしているように見えますか?
そうだとしたらそれは亡くなった私の母のおかげだと思います」と答えました。
その日の仕事が終った後、彼女はAさんからお母さんの話を詳しく聞きました。
Aさんは、お父さんが病気で小さい頃に亡くなってしまったため、お母さんに育てられたそうです。
お母さんは、仕事でどんなに疲れて帰ってきても、いつもAさんの前では笑顔でいたそうです。
ある日、Aさんが、
「どうして、お母さんはいつも楽しそうなの?
疲れたりしないの?」
と尋ねると、お母さんは、
「お母さんだって疲れているときや嫌な気分のときもあるよ。
でも、そんなときこそ、笑顔でいないといけないと思っているの。
ためしに笑顔を作ってごらん。
楽しい気分になるでしょ」と答えました。
Aさんがお母さんに言われた通りに笑顔を作ると、お母さんは、
「その笑顔を見たいから、お母さんはいつも笑顔でいるんだよ」
と微笑みながら話してくれたそうです。
最後にAさんは、彼女に向かって笑顔で言いました。
「家は貧乏で大変でしたが、母の笑顔のおかげでいつも楽しかったんです。
楽しいから笑顔でいるのではなくて、笑顔でいるから楽しくなるんですよ」
次の日、彼女はAさんのように朝から笑顔でいるように気をつけました。
すると、いつもはあまり話しかけてくれない人まで、
「おはよう、楽しそうだね」とか、
「今日はやけに機嫌がいいね」などと話しかけてくれました。
彼女の気持ちも自然に楽しくなりました。
笑顔の人の周りには、笑顔の人が集まってきます、だから、楽しいことも増えていくのです。
『会社に行くのがもっと楽しみになる感動の21話』三笠書房
「悲しいから泣くのではない、泣くから悲しいのだ」
という心理学の有名な言葉がある。
つまり、身体的な反応を意図的に起こせば、後からその感情がついてくるということ。
それは、楽しいという感情も同じ。
「楽しいから笑顔でいるのではない、笑顔でいるから楽しくなるのだ」
いつも不機嫌で、怒ったような顔をしていれば、
不平不満、文句や愚痴ばかり言う嫌なヤツになる。
人は、その表情や態度に似合った人になる。
いつも笑顔で機嫌よくしている人は、幸せを引き寄せる。

簡単な事のようですが難しい事ですよね~
その日の体調などに影響しますからね。
相手の表情や態度で、こちらもそうなりますよね。
今日も、皆様が笑顔で過ごせる一日になりますように

2013年05月19日
能力を伸ばす指導(接し方)とは・・・ 和歌山北高校体操部顧問・田中章二さんの言葉
致知2013年6月号 致知随想より
体操日本代表の田中三兄妹(和仁選手・佑典選手・理恵選手)の父親であり、
和歌山北高校体操部顧問・田中章二さんの言葉
人の話をよく聞いたり、場の空気を読めたりする精神年齢の高い子は上達も早いため、
そうした機会や課題をなるべく多く与えたいと考えてきた。
これは長男の和仁が3歳の時のこと。
スーパーへ行くと、キッズコーナーにお金を入れれば動く電動式の乗り物があった。
和仁は跨って遊んでいたが、
私は最初からお金を入れてやることはせず、その日はそのまま帰ることにした。
次に行った時、和仁の目線の先に、動いている乗り物で遊ぶ子供の姿があった。
和仁はその子が乗り物から降りるとすぐそちらへ駆けていったが、
止まってしまった乗り物はもう動いてはくれない。
3回目、和仁は自分は乗り物に乗ろうとはせず、やってきた親子連れの姿を見ていた。
そしてその親がお金を入れて乗り物が動くところを目にしたのだろう。
私のほうへ駆け寄ってきて、
「お父さん! あそこにお金を入れたら動くんや」
と実に嬉しそうに話をした。
その時、私は単にそうかとお金を渡すのではなく、
「おまえ、よう見抜いたなぁ!
自分で分からんことがあった時には、まず周りをよく見ることが大事なんや。
おまえは凄い。
きょうは好きなだけ乗せてやる」と誉めちぎった。
和仁は7回連続で心ゆくまで乗り物に乗った。
これと同じことがスポーツ指導にも言えるだろう。
大人に求められるのは子供が自ら考え、
答えを出すのをじっと待ってやることで、
端から正解を教えてしまっては本人の身にならない。
身体能力がいかに恵まれていても、
それだけで強くなっていけるのは小学校6年生程度までがせいぜいで、
頭を使えない子は必ず行き詰まってしまう。
子供が持つ可能性は無限だが、その能力を伸ばしてやるための環境づくりをし、
いかに本気に、真剣に取り組ませることができるかは、
我われ大人の役割であり、責任であると言えるだろう。
少しでも役割、責任が果たせるよう、
今日は、福岡まで勉強に行って来ます!

【パンフレット】
体操日本代表の田中三兄妹(和仁選手・佑典選手・理恵選手)の父親であり、
和歌山北高校体操部顧問・田中章二さんの言葉
人の話をよく聞いたり、場の空気を読めたりする精神年齢の高い子は上達も早いため、
そうした機会や課題をなるべく多く与えたいと考えてきた。
これは長男の和仁が3歳の時のこと。
スーパーへ行くと、キッズコーナーにお金を入れれば動く電動式の乗り物があった。
和仁は跨って遊んでいたが、
私は最初からお金を入れてやることはせず、その日はそのまま帰ることにした。
次に行った時、和仁の目線の先に、動いている乗り物で遊ぶ子供の姿があった。
和仁はその子が乗り物から降りるとすぐそちらへ駆けていったが、
止まってしまった乗り物はもう動いてはくれない。
3回目、和仁は自分は乗り物に乗ろうとはせず、やってきた親子連れの姿を見ていた。
そしてその親がお金を入れて乗り物が動くところを目にしたのだろう。
私のほうへ駆け寄ってきて、
「お父さん! あそこにお金を入れたら動くんや」
と実に嬉しそうに話をした。
その時、私は単にそうかとお金を渡すのではなく、
「おまえ、よう見抜いたなぁ!
自分で分からんことがあった時には、まず周りをよく見ることが大事なんや。
おまえは凄い。
きょうは好きなだけ乗せてやる」と誉めちぎった。
和仁は7回連続で心ゆくまで乗り物に乗った。
これと同じことがスポーツ指導にも言えるだろう。
大人に求められるのは子供が自ら考え、
答えを出すのをじっと待ってやることで、
端から正解を教えてしまっては本人の身にならない。
身体能力がいかに恵まれていても、
それだけで強くなっていけるのは小学校6年生程度までがせいぜいで、
頭を使えない子は必ず行き詰まってしまう。
子供が持つ可能性は無限だが、その能力を伸ばしてやるための環境づくりをし、
いかに本気に、真剣に取り組ませることができるかは、
我われ大人の役割であり、責任であると言えるだろう。
少しでも役割、責任が果たせるよう、
今日は、福岡まで勉強に行って来ます!

【パンフレット】
2013年05月15日
ある女性の人生最大の悔いとは・・・ 親の愛情がどんなに大切か!
母の日は過ぎましたが、素敵な記事ですのでご紹介を!
「魂が震える話」より
高校の頃とにかくバイトと遊びではしゃぎまくってた。
無免で中型乗って馬鹿だからマッポに捕まったりしてお母さんに迷惑かけまくった。
バイトもキャバクラと他に掛け持ちして
学校も公立の普通科で超多忙で通学費だけは自分で払ってた。
そんな中、高2~3までダイエットと忙しさで拒食症になった。
すごいガリガリになって普通の生活が辛くて眠くてイライラがずっとあった。
でもバイトも学校もしっかり行っていたが、
毎朝おかんが作るお弁当を全く食べずに家においていったままにした。
ほとんど食事をとらず友達にも家族にも相当心配かけてた時期。
家族との仲に溝ができて、会話がほとんどなかった。
しかしやっぱり人間の本能。
いずれ食欲は出て来て普通の生活が出来るようになり、今ではその反動がきてるw
拒食症の症状も軽くなった頃の高校卒業間際、学校最後のお弁当がある登校日。
久々の朝の会話
「お弁当忘れてるよ。」
その日学校で丁寧に包まれたお弁当ばこを開けた。
母からの手紙が。
あなたがダイエットをする頃から母はお弁当を作らなくなり、
悲しいような…楽チンだったような…
一時期は本当にどうなるのか不安で仕方ありませんでした。
たくさん心配かけることをしてくれたあなたですが体だけは健康にね。
いずれあなたにも子供ができて、
文句を言いながらお弁当を作る様子を思い浮かべると笑っちゃう。
でもあなたはママの娘。何があっても大丈夫。
これからも頑張ろうね。
学校で泣いた。友達に自慢しまくったw
泣きながら手紙入ってるよーって。
そのお弁当には私の大好きな母の手作りだし巻き卵焼きが入ってました。
うちのおかんは本当に料理がうますぎて、
ピザも生地から手作りで、味噌とかも家で作ってます。絶品。
今私は19歳。就職して1人暮らししています。
おかんのお弁当、なんでなんでもっと欲張って食べなかったんだろう。
人生最大の悔い。
今更だけどおかんのお弁当ってどれだけあったかくておいしかったのか思い知らされました。
あの愛情に勝てるものはこの世にないでしょう…
おかんみたいなおかんになることが私の夢です。

親の背中を見て子は育つ。
子は育てられた様に育つ。
子を見れば、どんな親か分かる。
子供が自慢出来る、親(大人)になりたいですね
良かったら、こちら(過去記事 親)もご覧になって見て下さい
「魂が震える話」より
高校の頃とにかくバイトと遊びではしゃぎまくってた。
無免で中型乗って馬鹿だからマッポに捕まったりしてお母さんに迷惑かけまくった。
バイトもキャバクラと他に掛け持ちして
学校も公立の普通科で超多忙で通学費だけは自分で払ってた。
そんな中、高2~3までダイエットと忙しさで拒食症になった。
すごいガリガリになって普通の生活が辛くて眠くてイライラがずっとあった。
でもバイトも学校もしっかり行っていたが、
毎朝おかんが作るお弁当を全く食べずに家においていったままにした。
ほとんど食事をとらず友達にも家族にも相当心配かけてた時期。
家族との仲に溝ができて、会話がほとんどなかった。
しかしやっぱり人間の本能。
いずれ食欲は出て来て普通の生活が出来るようになり、今ではその反動がきてるw
拒食症の症状も軽くなった頃の高校卒業間際、学校最後のお弁当がある登校日。
久々の朝の会話
「お弁当忘れてるよ。」
その日学校で丁寧に包まれたお弁当ばこを開けた。
母からの手紙が。
あなたがダイエットをする頃から母はお弁当を作らなくなり、
悲しいような…楽チンだったような…
一時期は本当にどうなるのか不安で仕方ありませんでした。
たくさん心配かけることをしてくれたあなたですが体だけは健康にね。
いずれあなたにも子供ができて、
文句を言いながらお弁当を作る様子を思い浮かべると笑っちゃう。
でもあなたはママの娘。何があっても大丈夫。
これからも頑張ろうね。
学校で泣いた。友達に自慢しまくったw
泣きながら手紙入ってるよーって。
そのお弁当には私の大好きな母の手作りだし巻き卵焼きが入ってました。
うちのおかんは本当に料理がうますぎて、
ピザも生地から手作りで、味噌とかも家で作ってます。絶品。
今私は19歳。就職して1人暮らししています。
おかんのお弁当、なんでなんでもっと欲張って食べなかったんだろう。
人生最大の悔い。
今更だけどおかんのお弁当ってどれだけあったかくておいしかったのか思い知らされました。
あの愛情に勝てるものはこの世にないでしょう…
おかんみたいなおかんになることが私の夢です。

親の背中を見て子は育つ。
子は育てられた様に育つ。
子を見れば、どんな親か分かる。
子供が自慢出来る、親(大人)になりたいですね

良かったら、こちら(過去記事 親)もご覧になって見て下さい

2013年05月12日
あなたは運が巡ってくる様にしてますか? 巡ってくる人とは・・・
吉元由美氏の心に響く言葉より…
軽い気持で、ある占星術で鑑定してもらったことがありました。
そのとき、
「あなたは36歳で死にます」
と言われたのです。
36歳までは10年を切っていました。
困ったなあ、というのが正直な思いです。
そのことを算命学の高尾先生に正直に話しました。
先生はいつものようににこにこ笑いながら、
「教科書通り」と答えました。
算命学においても、どうもその年にそんなことが起こりそうな「星」の組み合わせになるらしいのです。
「でも、大丈夫ですよ。死にませんから。それに36歳は結婚運も回ってますからね」
先生が死なないと言うのだから、死なないのだ。
そう思いました。
この間のプロセスについて思い出すと、今でも感慨深いのです。
生まれたときに、人間の運命がすべて定められているなんてことはありません。
ここで運が上昇し、ここからしばらく下降線に入る、といった大きな流れはあるでしょう。
でも生き方次第で大難は小難で乗り越えることができますし、難を回避することも出来るのです。
そうなるように選択し、生きればいいのです。
30歳で家を買う。
これまで上昇気流に乗って得た「財」をその時点で一度はき出すことにより、ゼロに引き戻す。
もしも私が「財」を出すことなく抱え込んでいたら、
たぶんその運の歪みは「病」という形で現れたのではないかと思います。
満杯になってしまった器にはそれ以上何も入らない。
一度、徹底的に空にしてしまう必要があったのです。
そして「自分が思っているよりも少し高い家を」という高島先生のアドバイスは、
自分の器を大きくするためと、セキュリティの意味があったのではないかと思うのです。
この推察はまったく「たら」「れば」の話なのですが、
30歳が「財」をゼロどころかマイナスにすることで、36歳の「死」を回避したのではないか、と。
生き方で運勢は変えられる、私はそう信じます。
『みんなつながっている ―ジュピターが教えてくれたこと―』小学館
吉元由美さんは、いままでに1000曲以上を作曲を手がけ、
中でも平原綾香が歌った「ジュピター」は東北大震災で傷ついた多くの人たちの心を癒し、涙をさそった。
あるお金持ちの老夫婦は、毎年決まって1ヶ月間、
田舎の決して立派ではない小さな旅館の小さな部屋にひっそり泊まる、という話を聞いたことがある。
それは、自分たちの運があまりにもよく、恵まれすぎているので、
それを少し散じて、不運を回避するためだという。
運も、お金も自分のためだけにため込むと、その反動があるといわれる。
多くの成功者たちは、人生の後半になって社会事業や、公のために財を散ずる。
運というものの本質を、本能的に知っているからかもしれない。
もし今、大病したとか、倒産したとか、
全てが裏目に出ているという状況にあるときは、運や財を散じている。
しかし、そのことによってもっと大きな不運を避けることができた、と考えたら気持は楽になる。
不運の時は、嘆いたり愚痴を言ったりしてはいけないといわれる。
それは、天が用意してくれた、
不運を避けるという大いなる「はからい」に対して文句を言うことになってしまうから。
「生き方で運勢は変えられる」
今を嘆かず文句を言わず、懸命に生きる人に運は巡ってくる。
わたくし、言わないようにと思っていますが~

日々、嘆いて文句を言ってるような・・・
まだまだだなぁ~
軽い気持で、ある占星術で鑑定してもらったことがありました。
そのとき、
「あなたは36歳で死にます」
と言われたのです。
36歳までは10年を切っていました。
困ったなあ、というのが正直な思いです。
そのことを算命学の高尾先生に正直に話しました。
先生はいつものようににこにこ笑いながら、
「教科書通り」と答えました。
算命学においても、どうもその年にそんなことが起こりそうな「星」の組み合わせになるらしいのです。
「でも、大丈夫ですよ。死にませんから。それに36歳は結婚運も回ってますからね」
先生が死なないと言うのだから、死なないのだ。
そう思いました。
この間のプロセスについて思い出すと、今でも感慨深いのです。
生まれたときに、人間の運命がすべて定められているなんてことはありません。
ここで運が上昇し、ここからしばらく下降線に入る、といった大きな流れはあるでしょう。
でも生き方次第で大難は小難で乗り越えることができますし、難を回避することも出来るのです。
そうなるように選択し、生きればいいのです。
30歳で家を買う。
これまで上昇気流に乗って得た「財」をその時点で一度はき出すことにより、ゼロに引き戻す。
もしも私が「財」を出すことなく抱え込んでいたら、
たぶんその運の歪みは「病」という形で現れたのではないかと思います。
満杯になってしまった器にはそれ以上何も入らない。
一度、徹底的に空にしてしまう必要があったのです。
そして「自分が思っているよりも少し高い家を」という高島先生のアドバイスは、
自分の器を大きくするためと、セキュリティの意味があったのではないかと思うのです。
この推察はまったく「たら」「れば」の話なのですが、
30歳が「財」をゼロどころかマイナスにすることで、36歳の「死」を回避したのではないか、と。
生き方で運勢は変えられる、私はそう信じます。
『みんなつながっている ―ジュピターが教えてくれたこと―』小学館
吉元由美さんは、いままでに1000曲以上を作曲を手がけ、
中でも平原綾香が歌った「ジュピター」は東北大震災で傷ついた多くの人たちの心を癒し、涙をさそった。
あるお金持ちの老夫婦は、毎年決まって1ヶ月間、
田舎の決して立派ではない小さな旅館の小さな部屋にひっそり泊まる、という話を聞いたことがある。
それは、自分たちの運があまりにもよく、恵まれすぎているので、
それを少し散じて、不運を回避するためだという。
運も、お金も自分のためだけにため込むと、その反動があるといわれる。
多くの成功者たちは、人生の後半になって社会事業や、公のために財を散ずる。
運というものの本質を、本能的に知っているからかもしれない。
もし今、大病したとか、倒産したとか、
全てが裏目に出ているという状況にあるときは、運や財を散じている。
しかし、そのことによってもっと大きな不運を避けることができた、と考えたら気持は楽になる。
不運の時は、嘆いたり愚痴を言ったりしてはいけないといわれる。
それは、天が用意してくれた、
不運を避けるという大いなる「はからい」に対して文句を言うことになってしまうから。
「生き方で運勢は変えられる」
今を嘆かず文句を言わず、懸命に生きる人に運は巡ってくる。
わたくし、言わないようにと思っていますが~

日々、嘆いて文句を言ってるような・・・
まだまだだなぁ~
2013年05月03日
離婚の原因1位は・・・ 相手が喜ぶポイントを見つける事が大切ですね(^-^)
「魂が震える話」より
恋愛や、夫婦間での問題解決になるかもしれません。
なぜ、うまくいかないのか?
なぜ、うまくいっているのか?
ヒントになればと思います。
ある弁護士さんに聞いたところ、
離婚原因の1位は、夫・妻、共に「性格が合わない」です。
よく芸能人も、
「価値観の違い」「性格の不一致」
と答える方が多いように思います。
最初は仲が良く、性格も分かったうえで結婚したはずなのに、なぜでしょう?
きっと、最初は相手に合わせていたからです。
年月が経ち、相手に合わせなくなっていきます。
そして見落としがちなのが、
してもらう事も、してあげる事も、人によって喜ぶポイントが違うということです。
大きく分けて4つの表現の仕方があります。
1,言葉
(「愛してるよ」「キレイだね」という言葉を言われたときに、愛情を感じるタイプ)
2,スキンシップ
(「キス」「ハグ」「頭を撫でられる」などのスキンシップを受けたときに愛情を感じるタイプ)
3,時間
(出来るだけ長い時間一緒にいたい。同じ時間を共有することによって愛情を感じるタイプ)
4,環境
(掃除や洗濯、料理などをしてもらうことによって愛情を感じるタイプ)
たとえば、自分が言葉のタイプで愛情を感じるとします。
この方は、いくら掃除や洗濯をしてもらっても“愛情”を感じにくいということです。
環境タイプの人にいくらハグしたって、たいして伝わらないんです。
では、
どうすれば相手のタイプが分かるのか?
 ここ大事です
ここ大事です
相手のタイプは、かなりの確率で、相手がしてくれている事と一緒です。
つまり、
「好きだ」と言ってくれる人には、こちらも「好きだ」と言う。
スキンシップが好きな人にはスキンシップを。
どこかに行ったり、同じ趣味をもったりして時間を共有したい人には、そうすべきです。
掃除、洗濯、料理を熟している人は、してもらうのも好き。
さらに、
これらをしてもらえない事による“怒り”さえも覚えるんです。
結果、「何もしてくれない」と言われるのです。
今回のGW、
普段出来ない所の掃除をしてみたり、
一緒にどこかに行ったり、スキンシップや言葉を意識してみては如何でしょうか♪
お互い好きで結婚したのですから、
相手の事を思いやり、素敵な人生にしたいものですね

恋愛や、夫婦間での問題解決になるかもしれません。
なぜ、うまくいかないのか?
なぜ、うまくいっているのか?
ヒントになればと思います。
ある弁護士さんに聞いたところ、
離婚原因の1位は、夫・妻、共に「性格が合わない」です。
よく芸能人も、
「価値観の違い」「性格の不一致」
と答える方が多いように思います。
最初は仲が良く、性格も分かったうえで結婚したはずなのに、なぜでしょう?
きっと、最初は相手に合わせていたからです。
年月が経ち、相手に合わせなくなっていきます。
そして見落としがちなのが、
してもらう事も、してあげる事も、人によって喜ぶポイントが違うということです。
大きく分けて4つの表現の仕方があります。
1,言葉
(「愛してるよ」「キレイだね」という言葉を言われたときに、愛情を感じるタイプ)
2,スキンシップ
(「キス」「ハグ」「頭を撫でられる」などのスキンシップを受けたときに愛情を感じるタイプ)
3,時間
(出来るだけ長い時間一緒にいたい。同じ時間を共有することによって愛情を感じるタイプ)
4,環境
(掃除や洗濯、料理などをしてもらうことによって愛情を感じるタイプ)
たとえば、自分が言葉のタイプで愛情を感じるとします。
この方は、いくら掃除や洗濯をしてもらっても“愛情”を感じにくいということです。
環境タイプの人にいくらハグしたって、たいして伝わらないんです。
では、
どうすれば相手のタイプが分かるのか?
 ここ大事です
ここ大事です相手のタイプは、かなりの確率で、相手がしてくれている事と一緒です。
つまり、
「好きだ」と言ってくれる人には、こちらも「好きだ」と言う。
スキンシップが好きな人にはスキンシップを。
どこかに行ったり、同じ趣味をもったりして時間を共有したい人には、そうすべきです。
掃除、洗濯、料理を熟している人は、してもらうのも好き。
さらに、
これらをしてもらえない事による“怒り”さえも覚えるんです。
結果、「何もしてくれない」と言われるのです。
今回のGW、
普段出来ない所の掃除をしてみたり、
一緒にどこかに行ったり、スキンシップや言葉を意識してみては如何でしょうか♪
お互い好きで結婚したのですから、
相手の事を思いやり、素敵な人生にしたいものですね


2013年04月20日
忘れていく事も大事ですが・・・ 忘却は、天が与えてくれた最高のプレゼント!
【人の心に灯をともす】http://merumo.ne.jp/00564226.htmlより
宇野千代さんの心に響く言葉より…
■私はいつの場合でも、自分に興味のあること、したいことを追い求めて忙しく生きてきた。
余りに忙しかったので、過ぎたことをくよくよしている暇はなかった。
思い出したくないことはつぎつぎ忘れさってしまった。
この忘れ去るという特技が、自分自身を救う一種の精神的治療法になったような気がしている。
■忘れるといことは新しく始めるということです。
心を空っぽにするから新しい経験を入れることが出来るのです。
いくつになっても人生は今日がはじまりである。
■人間らしい感覚を忘れ去るほどの忙しさ、
このやりきれない忙しさが、私を救ってきたのだと思います。
一身上のことでくよくよする時間がない、ということです。
私にも、考えようと思えばくよくよする種はあります。
しかし、そんな悩みは忙しさのために、
大風に吹きまくられた紙屑のように、眼にもとまらないのです。
■一歩踏み出せば凡(すべ)てが愉しい。
いつでも私は、そのときの生活に夢中になった。
そしてどうしても、どんなことがあっても、生きていたいと思った。
夢中で生きることが生きて行く目的であったからである。
「私は生きている」という発想から「私は生かされている」という発想に転換するとき、
周囲をとりまく自然の不思議さ、ありがたさに気がつくのである。
■人間は過去に生きるのではない。
新しい明日に向って生きるのだ。
私は、悲しみから心をはなし次の行動に向って心を動かす。
こうするのだと思った瞬間に、さっと体はその通りに動く。
いや、動くのではない。
もう踏み出しているのであった。
『宇野千代 幸福の言葉』海竜社
毎日が忙しく忙しくてたまらないような時には、悩みはそれほどない。
無我夢中で取り組んでいるから、余計なことは考えないからだ。
多くの人は、ヒマになったときに悩みが出てくる。
忙しいときは、今やらなければならないことや、
これからどうすればいいかを考えて行動するが、ヒマなときは過去のことにクヨクヨと悩む。
過去の嫌なことを事細かにすべて覚えていたら、
人は耐え切れず、気がおかしくなってしまうかもしれない。
「人に傷つけられたこと」、「暴言」、「暴力」、「痛み」、
「いじめ」、「裏切られたこと」、「失恋」、「親しい人の死」…
忘却は、天が与えてくれた最高のプレゼント。
忘れることができるから、明日も生きていける。
何かに没頭して忙しくすることは、過去の嫌なことにではなく、
目の前のやらなければいけないことに焦点をあてるということ。
どんなことでもいい、まず一歩を踏み出し、何かにのめりこみたい。

忘れる事も大切ですが、
しっかり反省してから忘れるようにしないとですね。
反省してからでないと成長に繋がらないと思うので!
わたくし小さな事での失敗が多くて、反省の日々が続いております。
成長してるのかなぁ~(笑)
宇野千代さんの心に響く言葉より…
■私はいつの場合でも、自分に興味のあること、したいことを追い求めて忙しく生きてきた。
余りに忙しかったので、過ぎたことをくよくよしている暇はなかった。
思い出したくないことはつぎつぎ忘れさってしまった。
この忘れ去るという特技が、自分自身を救う一種の精神的治療法になったような気がしている。
■忘れるといことは新しく始めるということです。
心を空っぽにするから新しい経験を入れることが出来るのです。
いくつになっても人生は今日がはじまりである。
■人間らしい感覚を忘れ去るほどの忙しさ、
このやりきれない忙しさが、私を救ってきたのだと思います。
一身上のことでくよくよする時間がない、ということです。
私にも、考えようと思えばくよくよする種はあります。
しかし、そんな悩みは忙しさのために、
大風に吹きまくられた紙屑のように、眼にもとまらないのです。
■一歩踏み出せば凡(すべ)てが愉しい。
いつでも私は、そのときの生活に夢中になった。
そしてどうしても、どんなことがあっても、生きていたいと思った。
夢中で生きることが生きて行く目的であったからである。
「私は生きている」という発想から「私は生かされている」という発想に転換するとき、
周囲をとりまく自然の不思議さ、ありがたさに気がつくのである。
■人間は過去に生きるのではない。
新しい明日に向って生きるのだ。
私は、悲しみから心をはなし次の行動に向って心を動かす。
こうするのだと思った瞬間に、さっと体はその通りに動く。
いや、動くのではない。
もう踏み出しているのであった。
『宇野千代 幸福の言葉』海竜社
毎日が忙しく忙しくてたまらないような時には、悩みはそれほどない。
無我夢中で取り組んでいるから、余計なことは考えないからだ。
多くの人は、ヒマになったときに悩みが出てくる。
忙しいときは、今やらなければならないことや、
これからどうすればいいかを考えて行動するが、ヒマなときは過去のことにクヨクヨと悩む。
過去の嫌なことを事細かにすべて覚えていたら、
人は耐え切れず、気がおかしくなってしまうかもしれない。
「人に傷つけられたこと」、「暴言」、「暴力」、「痛み」、
「いじめ」、「裏切られたこと」、「失恋」、「親しい人の死」…
忘却は、天が与えてくれた最高のプレゼント。
忘れることができるから、明日も生きていける。
何かに没頭して忙しくすることは、過去の嫌なことにではなく、
目の前のやらなければいけないことに焦点をあてるということ。
どんなことでもいい、まず一歩を踏み出し、何かにのめりこみたい。

忘れる事も大切ですが、
しっかり反省してから忘れるようにしないとですね。
反省してからでないと成長に繋がらないと思うので!
わたくし小さな事での失敗が多くて、反省の日々が続いております。
成長してるのかなぁ~(笑)
2013年04月19日
ブログで伝染する事が出来るように・・・
【人の心に灯をともす】http://merumo.ne.jp/00564226.htmlより
京都大学名誉教授、森毅氏の心に響く言葉より…
青春は輝かねばならない、と思い込んで、強迫観念になっている子が大学でも多い。
一番アホらしいパターンは「青い鳥シンドローム」。
学問であれ、スポーツであれ、友人関係であれ、
「輝かねば」という思いがあって、輝いていないと、
「ほかに輝くところがあるはずや」
と、青い鳥を求めてさまよいつづけることになる。
人生には晴れの日も曇りの日も嵐の日もある、まあ気楽にいこうや、と思っていたほうがいい。
あとになって、あの頃は輝いていたなあ、と思えればいいんだと。
親や先生が自分は輝いていないで、子どもだけ輝かそうというのは無理な話。
輝きは伝染するからね。
だいたい、親が悩んで暗くしていて、子どもが輝いていないと、文句言うのは筋違いだと思う。
輝くとは、何かにおもしろがっていたり、楽しみにしていることがあるということ。
それが何であろうとかまわないし、役にたたなくてもいいわけで、
人間はそれぞれ違うわけだから、本人にとって幸せな人生であればいい。
何かにおもしろがっていると、他人がそう気にならないし、愚痴や不満も少ない。
そういう人は他人から見ると、
「なんかこう、いい人生してはるなあ」
と思える。
考えようによっては、輝くなんて簡単なことだとも言える。
『人は一生に四回生まれ変わる』三笠書房
人が輝いて見えるときは、
何かに一心不乱に熱中しているときや、夢中で何かに打ち込んでいるときだ。
無我夢中のときは、不平や不満が出ない。
自分の関心事に集中していれば、人のことなど目に入らないからだ。
輝いているときは、どんなことでも、おもしろがってやっている。
だから、自然に笑みがこぼれ、機嫌よく、楽しそうに見える。
自分が、おもしろおかしく機嫌よくしていれば、まわりには自然に機嫌のいい人が集まる。
つまらなそうにしていれば、つまらない人が集まる。
「輝きは伝染する」
自分が輝けば、まわりも輝く。
わたくしがブログを楽しんでやってる事を見て頂き、
皆様に、楽しい伝染が出来るようになれば良いなぁ


【畳屋息子】 ブログ楽しんでますよ~
皆様にとって、今日も楽しい一日でありますように
京都大学名誉教授、森毅氏の心に響く言葉より…
青春は輝かねばならない、と思い込んで、強迫観念になっている子が大学でも多い。
一番アホらしいパターンは「青い鳥シンドローム」。
学問であれ、スポーツであれ、友人関係であれ、
「輝かねば」という思いがあって、輝いていないと、
「ほかに輝くところがあるはずや」
と、青い鳥を求めてさまよいつづけることになる。
人生には晴れの日も曇りの日も嵐の日もある、まあ気楽にいこうや、と思っていたほうがいい。
あとになって、あの頃は輝いていたなあ、と思えればいいんだと。
親や先生が自分は輝いていないで、子どもだけ輝かそうというのは無理な話。
輝きは伝染するからね。
だいたい、親が悩んで暗くしていて、子どもが輝いていないと、文句言うのは筋違いだと思う。
輝くとは、何かにおもしろがっていたり、楽しみにしていることがあるということ。
それが何であろうとかまわないし、役にたたなくてもいいわけで、
人間はそれぞれ違うわけだから、本人にとって幸せな人生であればいい。
何かにおもしろがっていると、他人がそう気にならないし、愚痴や不満も少ない。
そういう人は他人から見ると、
「なんかこう、いい人生してはるなあ」
と思える。
考えようによっては、輝くなんて簡単なことだとも言える。
『人は一生に四回生まれ変わる』三笠書房
人が輝いて見えるときは、
何かに一心不乱に熱中しているときや、夢中で何かに打ち込んでいるときだ。
無我夢中のときは、不平や不満が出ない。
自分の関心事に集中していれば、人のことなど目に入らないからだ。
輝いているときは、どんなことでも、おもしろがってやっている。
だから、自然に笑みがこぼれ、機嫌よく、楽しそうに見える。
自分が、おもしろおかしく機嫌よくしていれば、まわりには自然に機嫌のいい人が集まる。
つまらなそうにしていれば、つまらない人が集まる。
「輝きは伝染する」
自分が輝けば、まわりも輝く。
わたくしがブログを楽しんでやってる事を見て頂き、
皆様に、楽しい伝染が出来るようになれば良いなぁ



【畳屋息子】 ブログ楽しんでますよ~

皆様にとって、今日も楽しい一日でありますように

2013年04月12日
こんな話をして頂いたのを思い出しましたので・・・
前記事に続き、
稲盛和夫さんの本を読んで思い出した事で・・・
10年程、もっとなるかなぁ~
わたくしが、22~23歳の頃でしたか・・・
お世話になっている方から、こんなお話をお聞きしました。
私達が若い頃は、
給料が安くても会社の為(大きくしたい)、お客さんの為と思って仕事をしました。
そして皆で頑張った結果、今は大きな会社になりました。
今の若い方は(全ての人ではないが)、
給料が良い悪いで判断して会社を決めていますよね。
そういう自分の事しか考えてない人は、
やっぱり、長続きしない・良い仕事が出来ない人が多いですね・・・。
最近、お話しした方からは、
「あなたがずっと必要だ、あなたには辞めないで頂きたい」、
こんな事を言って頂けるまでは、
どんな事があろうとも辞めないで会社の為に頑張ろうと考えてました。
こういう事を言って頂ける様になりましたので、
辞めて、今この仕事をしているんですよ。
嫌になり、そこから逃げても、また同じ試練が待っていると思います。
周りの方々に感謝し、働く事が大切ですね。
こういった、素敵なお話を聞く事が出来ました。
前記事でご紹介させて頂きました、
「動機善なりや 私心なかりしか」
この気持ちを持っていれば、素晴らしい働き方が出来るものと信じています!

稲盛和夫さんの本を読んで思い出した事で・・・
10年程、もっとなるかなぁ~
わたくしが、22~23歳の頃でしたか・・・
お世話になっている方から、こんなお話をお聞きしました。
私達が若い頃は、
給料が安くても会社の為(大きくしたい)、お客さんの為と思って仕事をしました。
そして皆で頑張った結果、今は大きな会社になりました。
今の若い方は(全ての人ではないが)、
給料が良い悪いで判断して会社を決めていますよね。
そういう自分の事しか考えてない人は、
やっぱり、長続きしない・良い仕事が出来ない人が多いですね・・・。
最近、お話しした方からは、
「あなたがずっと必要だ、あなたには辞めないで頂きたい」、
こんな事を言って頂けるまでは、
どんな事があろうとも辞めないで会社の為に頑張ろうと考えてました。
こういう事を言って頂ける様になりましたので、
辞めて、今この仕事をしているんですよ。
嫌になり、そこから逃げても、また同じ試練が待っていると思います。
周りの方々に感謝し、働く事が大切ですね。
こういった、素敵なお話を聞く事が出来ました。
前記事でご紹介させて頂きました、
「動機善なりや 私心なかりしか」
この気持ちを持っていれば、素晴らしい働き方が出来るものと信じています!

2013年04月12日
働く皆様へ~ 最高の働き方【人生で「価値あるもの」を手に入れる方法】
欲しい本を買いに行ったら、
この本も↓読んでみたいなと思い購入しました!

【働き方 稲盛和夫氏】
「働く」ということは~
試練を克服し、運命を好転させてくれる、まさに「万病に効く薬」
今の自分の仕事に、もっと前向きに、
できれば無我夢中になるまで打ち込んでみてください。
そうすれば必ず、苦難や挫折を克服する事ができるばかりか、
想像もしなかったような、新しい未来が開けてくるはずです。
本書を通じて、一人でも多くの方が、「働く」ことの意義を深め、
幸福で素晴らしい人生を送っていただくことを心から祈ります。
稲盛さんが、
仕事や人生を実り多きものにしてくれる、正しい「考え方」をご紹介されています。(エピローグより)
つねに前向きで、建設的であること。
みんなと一緒に仕事をしようと考える協調性を持っていること。
明るい思いを抱いていること。
肯定的であること。
善意に満ちていること。
思いやりがあって、優しいこと。
真面目で、正直で、謙虚で、努力家であること。
利己的ではなく、強欲ではないこと。
「足るを知る」 心を持っていること。
そして、感謝の心を持っていること。
将来を担うべき、若い読者のみなさんが、このような「考え方」を持って
一生懸命に働くことを通じて、素晴らしい人生を歩まれることを心から願っています。
働く事の素晴らしさを、改めて感じました
稲盛さんの好きな言葉で、以前ご紹介させて頂いた言葉
「動機善なりや、私心なかりしか」
仕事で悩んだり、行き詰っている方、そして、働いている方に!
「なぜ働くのか、いかに働くのか」
稲盛さんの本、オススメですよ
この本も↓読んでみたいなと思い購入しました!

【働き方 稲盛和夫氏】
「働く」ということは~
試練を克服し、運命を好転させてくれる、まさに「万病に効く薬」
今の自分の仕事に、もっと前向きに、
できれば無我夢中になるまで打ち込んでみてください。
そうすれば必ず、苦難や挫折を克服する事ができるばかりか、
想像もしなかったような、新しい未来が開けてくるはずです。
本書を通じて、一人でも多くの方が、「働く」ことの意義を深め、
幸福で素晴らしい人生を送っていただくことを心から祈ります。
稲盛さんが、
仕事や人生を実り多きものにしてくれる、正しい「考え方」をご紹介されています。(エピローグより)
つねに前向きで、建設的であること。
みんなと一緒に仕事をしようと考える協調性を持っていること。
明るい思いを抱いていること。
肯定的であること。
善意に満ちていること。
思いやりがあって、優しいこと。
真面目で、正直で、謙虚で、努力家であること。
利己的ではなく、強欲ではないこと。
「足るを知る」 心を持っていること。
そして、感謝の心を持っていること。
将来を担うべき、若い読者のみなさんが、このような「考え方」を持って
一生懸命に働くことを通じて、素晴らしい人生を歩まれることを心から願っています。
働く事の素晴らしさを、改めて感じました

稲盛さんの好きな言葉で、以前ご紹介させて頂いた言葉
「動機善なりや、私心なかりしか」
仕事で悩んだり、行き詰っている方、そして、働いている方に!
「なぜ働くのか、いかに働くのか」
稲盛さんの本、オススメですよ

2013年04月11日
あなたは、この様な人をどう思いますか! 大切なモノを捨てている人・・・
【人の心に灯をともす】http://merumo.ne.jp/00564226.html より
souji出典:志賀内康弘著『なぜ「そうじ」をすると人生が変わるのか?』ダイヤモンド社
「ゴミを1つ捨てる者は、大切な何かを1つ捨てている
ゴミを1つ拾う者は、大切な何かを1つ拾っている」
これは私の「そうじの師」から教えていただいた金言です。
師は、1年間に10万本の吸殻を拾って歩いていました。
毎日300本です。
それも75歳になってから始め、10年後の85歳になったとき、100万本を達成しました。
バスでも電車でも、
どこへ行くときにも右手には金バサミ、左手には紙袋を持って拾い続けられました。
「大切な何かを拾っている」とは何なのか。
「品格」「こころ」「おもいやり」「自尊心」「高潔」「公共心」「道徳心」「魂」「礼節」…
人によってさまざまな言葉が当てはまると思います。
その中でも、私は「信用」という言葉を一番に上げたいと思います。
人の目の前でポイッとゴミを捨てる人を、あなたは「信用」できるでしょうか。
空き缶を車の窓から中央分離帯へ投げ捨てる人。
タバコの吸殻を、舗道に捨てる人。
その人たちは、実は、自分の一番大切な「信用」を捨てているのです。
いくらお金持ちでも、どれほど大きな会社の社長さんでも、
「空缶のポイ捨て」をするような人とは付き合いたくありません。
もし、そういう人と、友達だと見られるだけで、こちらの「信用」が落ちてしまいます。
数年前に「お金で買えないものはない」という発言が物議を醸したことがありますが、
たとえ「お金で信用を買える」としても、
「お金で買った信用」は、お金がなくなれば、一緒に消えてしまいます。
タバコの吸殻や、空缶などをポイッと捨てる人は、
誰かがそこをキレイにしていることに気づかない。
中央分離帯にしても、道路にしても、公園にしても、そこをキレイにしている人がいる。
もし、自分の家や玄関ドアの前に、
タバコの吸殻や空缶がいつも捨ててあったらどんな気持になるだろう。
ゴミを捨てる、という人は、甘えのあるワガママな子供と同じ。
誰も見ていなければ、落書きしてもいい、トイレや洗面所を汚して出ていってもいい、
そして、少しぐらいなら万引きしてもいい、とどんどんエスカレートする。
真の大人は、人が見ていないときほど、自分を律し、自分に厳しい。
幼い頃からの躾が大事という事でしょうね!
信用される人が増える事を願います。

ゴミを捨てる人がいなくなり、素敵な日本になりますように!
souji出典:志賀内康弘著『なぜ「そうじ」をすると人生が変わるのか?』ダイヤモンド社
「ゴミを1つ捨てる者は、大切な何かを1つ捨てている
ゴミを1つ拾う者は、大切な何かを1つ拾っている」
これは私の「そうじの師」から教えていただいた金言です。
師は、1年間に10万本の吸殻を拾って歩いていました。
毎日300本です。
それも75歳になってから始め、10年後の85歳になったとき、100万本を達成しました。
バスでも電車でも、
どこへ行くときにも右手には金バサミ、左手には紙袋を持って拾い続けられました。
「大切な何かを拾っている」とは何なのか。
「品格」「こころ」「おもいやり」「自尊心」「高潔」「公共心」「道徳心」「魂」「礼節」…
人によってさまざまな言葉が当てはまると思います。
その中でも、私は「信用」という言葉を一番に上げたいと思います。
人の目の前でポイッとゴミを捨てる人を、あなたは「信用」できるでしょうか。
空き缶を車の窓から中央分離帯へ投げ捨てる人。
タバコの吸殻を、舗道に捨てる人。
その人たちは、実は、自分の一番大切な「信用」を捨てているのです。
いくらお金持ちでも、どれほど大きな会社の社長さんでも、
「空缶のポイ捨て」をするような人とは付き合いたくありません。
もし、そういう人と、友達だと見られるだけで、こちらの「信用」が落ちてしまいます。
数年前に「お金で買えないものはない」という発言が物議を醸したことがありますが、
たとえ「お金で信用を買える」としても、
「お金で買った信用」は、お金がなくなれば、一緒に消えてしまいます。
タバコの吸殻や、空缶などをポイッと捨てる人は、
誰かがそこをキレイにしていることに気づかない。
中央分離帯にしても、道路にしても、公園にしても、そこをキレイにしている人がいる。
もし、自分の家や玄関ドアの前に、
タバコの吸殻や空缶がいつも捨ててあったらどんな気持になるだろう。
ゴミを捨てる、という人は、甘えのあるワガママな子供と同じ。
誰も見ていなければ、落書きしてもいい、トイレや洗面所を汚して出ていってもいい、
そして、少しぐらいなら万引きしてもいい、とどんどんエスカレートする。
真の大人は、人が見ていないときほど、自分を律し、自分に厳しい。
幼い頃からの躾が大事という事でしょうね!
信用される人が増える事を願います。

ゴミを捨てる人がいなくなり、素敵な日本になりますように!